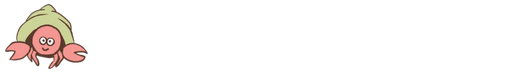こんにちは!お絵描きブロガーのヤドカリコ(@yadokarikodayo)です。
本日4月1日、ついに新元号が発表されましたね!
それはなんと…
「令和(れいわ)」!
思っていたより、すっきりした文字並び…!
この発表に、Twitterでの反応は上々な感じです。
【お知らせ】新元号は「令和」に決まりました。
— 首相官邸 (@kantei) 2019年4月1日
今回の記事では、新元号「令和」の由来や豆知識・作者についても、わかりやすくご紹介いたします。
サクッと読める記事ですので、ぜひ学校や会社での話題にご活用ください!
万葉集「梅花の歌」からの出典:新元号「令和(れいわ)」意味と由来

新元号「令和」の由来は、「万葉集」の梅花の歌が出典です。
下記から、「令和」の出典元である「万葉集」を中心に、わかりやすく解説していきますね。
「万葉集」とは、奈良時代の日本最古の歌集
「万葉集」は日本最古の歌集です。

全20巻あり、7~8世紀ごろ(奈良時代)に現在の形に近いものに、まとめられたと言われています。
「万葉集」は、天皇や皇族、歌人、さらには農民など幅広い階層の人々が読んだ「約4,500首」の歌が収められています。
国語の授業でも取り上げられるので、ご存知の方も多いですよね。
首相は、万葉集について「幅広い階層の人が読んだ歌が収められており、豊かな文化と伝統を象徴している国書である」と話しています。
新元号「令和」の意味とは:首相談話より
首相官邸で発表された、新年号「令和」の意味をご紹介します。
春の訪れを告げ、
見事に咲き誇る梅の花のように
一人ひとりが明日への希望とともに、
それぞれの花を大きく咲かせることができる、
そうした日本でありたいとの願いを込め、決定した。日経新聞(2019年4月2日号)より引用
「明日への希望と共に、日本人1人ひとりが大きな花を咲かせる」という願いを込めて、「令和」という文字が選ばれたのですね。
この「令和」という言葉は、日本最古の歌集「万葉集」の”梅花の歌”から採用されています。
万葉集「梅花の歌」の作者・本文をわかりやすく解説!
 新元号「令和」の出典元である「梅花の歌」は、万葉集5巻に収録されています。
新元号「令和」の出典元である「梅花の歌」は、万葉集5巻に収録されています。
万葉集「梅花の歌」の作者:大伴旅人の作と言われている
万葉集「梅花の歌」の作者は、大伴旅人(おおとも の たびと)といわれています。しかし諸説ありますので、作者不明ということです。
大伴旅人は、飛鳥時代から奈良時代に活躍した歌人で、太宰府長官でもありました。
―万葉集「梅花の歌」―
初春の令月にして、
気淑(よ)く風和ぎ、
梅は鏡前の粉(こ)を披(ひら)き、
蘭は珮後(はいご)の香を薫(かをら)す。―万葉集入門より引用―
この歌は730年、大伴旅人の同僚や友人を招いた宴で「梅に関する和歌」を32首、詠まれました。梅の開花とともに、春の訪れを喜んだ内容です。
そのときの序文として、この「梅花の歌」が寄せられたとのことです。
この歌から、新元号「令和」が引用されました。
令和の「令」の由来:梅花の歌「初春の令月」から引用

ここで令和の「令」という文字の由来をご紹介します。
由来元の万葉集「梅花の歌」の歌の中に「初春の令月」という言葉があります。
【意味】
何事をするにもよい月。めでたい月。
新元号にぴったりの、おめでたい言葉なのですね!
「令」という文字が元号に使われるのは初めて!
新元号「令和」ですが、「令」という文字が使われるのは、今回が初めて!
これまでの日本の元号は、すべて中国の古典からの由来でした。
しかし今回の「令和」は、初めての日本の古典が由来となりました。
首相によると「日本の四季折々の文化と自然を、これからの世代にも引き継いでいきたい」という思いで、万葉集から引用しているとのことです。
「和」の漢字使用は20回目!:新元号「令和」豆知識
ちなみに「和」という漢字が元号に使用されたのは、過去に20回もあります!
わたしが思いつくだけでも「昭和(しょうわ)」「享和(きょうわ)」などがありますね。
「令和」は、日本最初の元号「大化」から248番目にあたります。
さいごに:新元号「令和(れいわ)」は2019年5月1日に改元!

以上、新元号「令和(れいわ)」について、わかりやすく解説しました。
日本の四季折々の文化を、次の世代に引き継ぐという思いが込められた「令和」。
これを機に、万葉集を読み返したくなりましたね…!
2019年5月1日には改元され、新元号「令和(れいわ)」が始まります。
新年度、気持ちを新たに「令和(れいわ)」を迎えましょう!
ヤドカリコでした!

▼「お絵かきフリーランス」奮闘記を発信中!▼